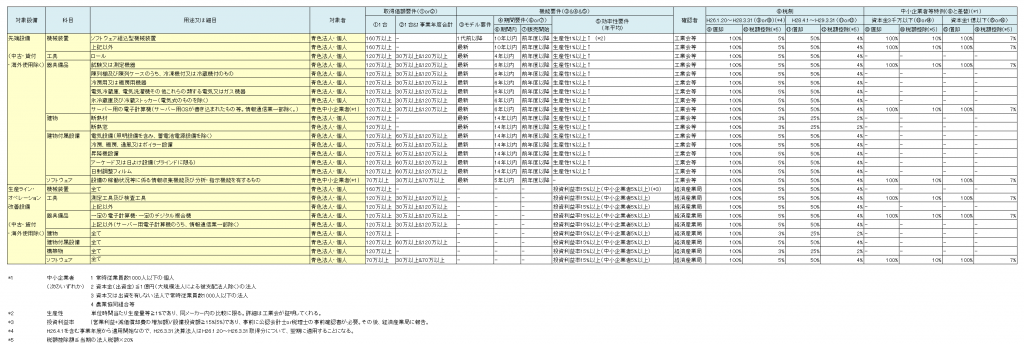「競馬の配当に対し課税する際、はずれ馬券の購入費を経費にできるか否か?」について争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、はずれ馬券も経費にあたると判断しました。
訴状によると原告は、過去に競馬の予想ソフトを使って35億1千万円の馬券を購入。そこから36億6千万円の配当を得たが申告をしなかったとのこと。
無申告が有罪なのはまぁ当然として、ここで争われたのは”経費”の額です。原告ははずれ馬券も含めた全ての馬券購入費35億1千万円を経費と主張し、課税当局は当たり馬券の購入費1億8千万円のみを経費と主張しているようです。結果、大阪地裁は原告の主張を認める判断を下しました。
これはすなわち競馬配当を「雑所得」として捉えるのか、あるいは「一時所得」として捉えるかの争いです。原告は雑所得として、課税当局は一時所得として主張しています。
雑所得は「総収入金額-必要経費」で計算され、必要経費の中にははずれ馬券も含まれるというのが原告の主張です。
一方で、一時所得は「収入額―収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、”収入を得るために支出した金額”とは当然、当たり馬券の購入費のみというのが課税当局の主張です。
・・・どちらの言い分もわかるのですが、個人的には原告側かも。
一時所得の定義が、営利を目的とする継続的行為から生じた所得”以外”の所得となっており、原告のこの購入スタイルはどう考えても営利目的の継続行為でしょう。
あと、人情的にも「はずれ馬券という”屍”を乗り越え、当たり馬券という”栄光”を勝ち取った!」と考える方がストーリーとして俄然、盛り上がります(笑)